登録後、すべての物件が閲覧可能になります!
また、会員様には一般公開より先にお得な物件情報をメールで配信中!
(配信不要の方はお手数ですが、登録後にメルマガ配信解除の手続きを行ってください)
不動産価格の決まり方!
不動産会社の査定と不動産鑑定士の評価の違い
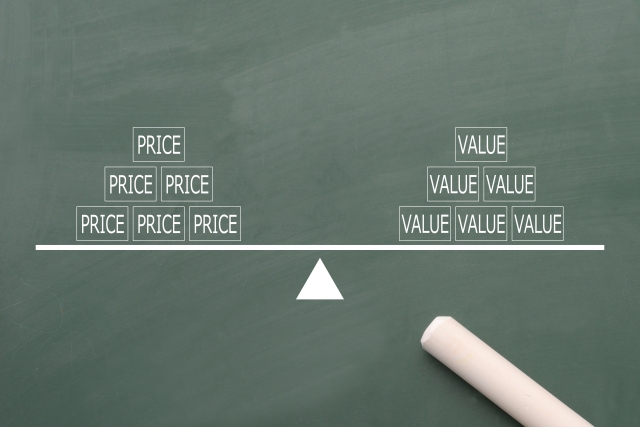
不動産情報サイトを見ていて、ほとんど同じ条件の物件で微妙に価格が違うことに疑問を持ったことはないでしょうか?
同じ条件なのに価格に大きな差があるという場合もあります。
不動産価格は市場相場の影響を受けますが、物件価格に差があるということはその物件に関して何らかの事情があることが予想されます。
ではその事情とは何でしょうか。
今回は不動産価格の決まり方を分かりやすく解説します。
あまり知られていない銀行が不動産価値を見極める際の計算方法も解説しますので、ぜひご参考になさってください!
不動産価格が決まる多くの要素
不動産価格といっても「土地」「建物」に分かれますが、それぞれの価格はたくさんの要素を加味して決められます。
具体的にどのような要素があるのか見てみましょう。
【土地価格が決まる要素】
土地の形状
接道状況
公示地価や路線価
地域性
売り主の意向
過去の取引事例
など
【建物価格が決まる要素】
築年数
大きさなどの規模
構造や各部の材質
設備のグレード
耐震性や耐火性
リフォームの有無
固定資産税評価額を基にした算出
売り主の意向
過去の取引事例
など
例えば土地に関しては「整形地(道路に面した四角形の土地)」や「かぎ型地(通路の奥にある土地)」、「ウナギの寝床(縦に長い土地)」などで土地の評価が大きく変わります。
基本的には道路に面している整形地は資産価値が高くなり、形が崩れるほど資産価値は低くなるのです。
また建物は、駅から近いかどうかという地域性よりも、築年数や利用価値、瑕疵の有無、構造、各部の材料などで評価が変わります。
建物は考慮するものが非常に多いため、土地よりも価格の決め方は難しいということだけ覚えておきましょう。
不動産会社の査定と不動産鑑定士の査定の違い
前章でお伝えしたとおり、不動産の売買価格は様々な要素を加味して決定します。
ただ不動産価格が決められる際の慣行としては、以下2つの方法に分かれるのが一般的です。
不動産会社が周辺相場や現地調査、過去の取引事例、経験などを基にして査定する
前章で挙げた項目を全て洗い出し、加点や減点、緻密な計算などを行いながら決定する
「1」の査定方法は不動産会社が多く使う手法で「取引事例比較法」と言います。
「2」は主に不動産鑑定士などが行う評価方法で、「積算価格」「収益還元法」「DCF法」など実に難解な計算方法を用いなければなりません。
結局のところ上記2つのうち、どちらの方法で価格が決められるかは査定などを依頼した業者により違うということです。
では上記のどちらが正解かというと、実はどちらも正解不正解ということはありません。
なぜなら、いくら細かく試算したとしても最終的に「なるべく高く売りたい」「安くていいから早く売りたい」といった売り主の意向に左右されるためです。
ただ「それでも自分が所有する不動産の価格を正確に知りたい!」という方もいらっしゃるかと思います。
そこで次の章では不動産鑑定士や銀行の担当者が特に気にする不動産の資産価値について詳しく解説します。
不動産鑑定士や銀行による不動産の評価方法
不動産鑑定士や銀行などが不動産の資産価値を見るときには複雑な計算で価格を算出します。
先ほどお伝えした計算方法の違いを簡単にご説明します。
積算価格 予め決められた一定の評価額で計算した土地と建物の価値を合算する計算方法
収益還元法 その不動産が生み出す収益性から逆算して資産価値を決める計算方法
DCF法 将来に渡って資産価値が落ちる割合を加味しながら計算する方法
積算価格:予め決められた一定の評価額で計算した土地と建物の価値を合算する計算方法
収益還元法:その不動産が生み出す収益性から逆算して資産価値を決める計算方法
DCF法:将来に渡って資産価値が落ちる割合を加味しながら計算する方法
上記のうちDCF法と収益還元法が非常に難解で、全てを解説するにはこのページだけでは難しいため別の機会に解説させていただければと思います。
残る「積算価格」は比較的に考え方を簡素化することができます。
まず計算式を見てみましょう。
積算価格の計算方法
1㎡あたりの土地価格 × 土地面積 = 土地の資産価値(A)
再調達原価 × 延べ床面積 × (残存耐用年数 ÷ 耐用年数) = 建物の資産価値(B)
(A) + (B) = 積算価格
「1㎡あたりの土地価格」とは「公示地価」「相続税路線価」「固定資産路線価」などが使われますが、銀行が資産価値を決める場合や不動産会社が査定する場合など目的により違います。
資産価値を見極めるという点では、相続税路線価を使用するのが一般的です。
また再調達原価とは1㎡あたりの建物原価ということですが、これもまた複雑な考え方で成り立つものです。
一般的なところでは以下が基準になっています。
一般的な再調達原価
鉄筋コンクリート 18~20万円
重量鉄骨 15~18万円
木造・軽量鉄骨 12~15万円
鉄筋コンクリート:18~20万円
重量鉄骨:15~18万円
木造・軽量鉄骨:12~15万円
そして耐用年数は税法上で以下のように定められています。
建物別の耐用年数
鉄筋コンクリート:47年
重量鉄骨:34年
軽量鉄骨:19年 or 27年 (鉄骨の厚さにより異なる)
木造:22年
これらの要素を上記の式に当てはめて計算すると積算価格が算出できます。

積算価格をシミュレーション!結局どの査定方法が良い?
さて、ここまで不動産価格の決め方は色々な方法があるということを解説させていただきましたが、前章で解説した積算価格による不動産価格をシミュレーションしてみましょう。
物件種別:木造アパート
土地面積:50坪(約165㎡)
路線価:9.2万円(㎡単価)
延べ床面積: 264㎡
築年数:15年
上記の物件の土地価格は以下の計算になります。
9.2万円 × 165㎡ = 1518万円
建物の計算は以下のようになります。
12~15万円 × 264㎡ × (残存耐用年数7年 ÷ 木造耐用年数22年) = 1008~1260万円
最終的に両方をプラスします。
1518万円 + 1008~1260万円 = 2526~2778万円
このアパートの資産価値は「2526~2778万円」という結果になりました。
「アパートなのに安い」と思われるかもしれませんが、エリアや築年数、構造によって不動産価格は全く違うということの現れと言えるでしょう。
ただ、積算価格はあくまで銀行などが資産価値を決める一つの目安ということに注意しましょう。
つまり収益物件へ融資するために担保価値を見極めるのが積算価格であり、本来の不動産取引の価格とは違うこともあるのです。
ここまで解説させていただいてからの注意点ですから「じゃあ、どの方法が一番正しい方法なの?」と混乱するかもしれませんが、以下のように考えると分かりやすいでしょう。
積算価格・収益還元法・DCF法など:銀行や不動産鑑定士が不動産の担保価値を決めるための計算方法
取引事例比較法:不動産会社や買取業者と相談して相場に沿いながら有利な売買価格を決めるための方法
つまり、正確な資産価値を見極めたいとか銀行融資における担保評価を気にするということでもない限り、相場から大きく外れない範囲で不動産屋さんや査定会社と相談して決めた価格も売り主にとって適正価格なのです。
とはいえ、近隣の売り物件と自分の所有する不動産を比較して「大体このくらいかな」と曖昧に資産価値を決めてしまうと、売るに売れない、または安くしすぎてしまったなどの失敗に繋がります。
今回ご紹介したような計算方法などを用いることで「このくらいの価格なら融資が付くから、ローンで買ってくれる人も視野に入る」「遺産分割をしたいから積算より安くても早く売りたい」などの目的別で価格を決めることができます。
不動産価格の決め方を積極的に学んで戦略的な価格決定ができれば、きっと役に立つ日も来るでしょう。